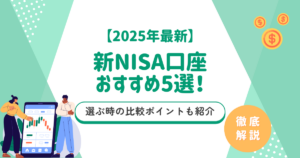- 新NISAを始めるにはもう遅いのか教えてほしい
- 新NISAで毎月どのくらい積立すればいいのか知りたい
- 新NISAでどのような銘柄に投資すべきかわからない
2024年に開始された新NISAは、40代からでも十分に資産形成のチャンスがある仕組みだ。
「40代で今さら始めても遅いのでは?」と感じる人もいるかもしれないが、40代はまだまだ老後までに時間があるため、複利効果を最大限に活かして資産を大きく増やすことができる。
2種類の非課税枠をうまく組み合わせれば、リスクヘッジと高いリターンの両方を狙うことも可能だ。
本記事では、40代が新NISAを始めるべき理由や、具体的な運用方法やおすすめ銘柄、新NISAを利用する際の注意点について詳しく解説する。
資産形成は早く始めるほど効果的なので、ぜひこの機会に新NISAでの運用を始めてみてはいかがだろうか。
40代からでも遅くない!今すぐ新NISAを始めるべき理由

「40代で新NISAを始めても遅いかも」と考えている人がいるかもしれないが、それは誤りだ。
まずは、40代の人がどの程度新NISAを利用しているかや、なぜ40代が新NISAを始めた方が良いのかをチェックしていこう。
40代の新NISA利用状況
金融庁が実施した「NISA口座の利用状況調査」によると、2024年9月末時点での40代のNISA口座数は482万6,897口座となっている。
特に、新NISAが始まった2024年前後では口座開設数が大きく伸びた。
なお、各年代における保有口座数や年代別比率は下記の通りだ。
| 口座数 | 年代別比率 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,508万6,221口座 | 100.0% |
| 10歳代 | 12万8,936口座 | 0.5% |
| 20歳代 | 287万8,530口座 | 11.5% |
| 30歳代 | 439万1,484口座 | 17.5% |
| 40歳代 | 482万6,897口座 | 19.2% |
| 50歳代 | 481万864口座 | 19.2% |
| 60歳代 | 369万1,248口座 | 14.7% |
| 70歳代 | 285万8,589口座 | 11.4% |
| 80歳代以上 | 149万9,673口座 | 6.0% |
また、三井住友トラスト・資産のミライ研究所の「住まいと資産形成に関する意識と実態調査(2025年)」によると、NISA制度に対する40代の認知度・利用度は以下のような結果となった。
NISA制度を「知っている」・「利用している」の割合(40代)
| 知っている | 利用している |
|---|---|
| 59.6% | 22.4% |
NISA制度の認知度が約6割となっている一方で、実際に利用している人の割合は約2割強とまだそれほど多くないと言える。
また、NISAの利用意向に関する質問に対しては、以下のような回答結果となった。
NISAの利用者割合と未利用者における利用意向(40代)
| 利用済 | 22.4% |
|---|---|
| 利用する | 2.3% |
| おそらく利用する | 10.6% |
| どちらともいえない | 32.7% |
| おそらく利用しない | 12.6% |
| 利用しない | 19.3% |
今後のNISAの利用については「どちらともいえない」と迷っている人が多いようだ
「40代で投資を始めても遅いのかもしれない」「今更投資の勉強をするのはハードルが高い」と、40代で投資を始めることに抵抗を感じている人が少なからずいると考えられる。
一方で、40代は昇進したり家族が増えたりと、ライフイベントが変わったりする時期である。
また、老後の生活についてもある程度具体的なイメージを持ちやすくなってくる年代でもあるだろう。
40代は「老後」までにはまだ時間があるとはいえ、老後に向けて資金面でしっかりと準備をしないと、満足のいく老後生活を送れない可能性がある。
豊かな老後生活を送るためには、老後に必要なお金や現在の貯蓄額を確認しつつ、適切な方法で資産運用を始めることが重要だ。
40代から新NISAで運用を始めるメリット
40代から新NISAで投資を始めるメリットは、主に以下の3点だ。
- 長期目線で運用できる
- 少額の積立でも大きな資産になる
- 非課税効果を長期間受けられる
長期目線で運用できる
40代から新NISAを始めることで、一般的に20年以上の運用期間が確保できる。長期運用を前提に売れば、相場の短期的な変動に一喜一憂する必要はなく、落ち着いた心持ちで資産形成が可能だ。
特に、特定の指数に連動するパフォーマンスを目指すインデックスファンドを活用した分散投資であれば、長い目で見たときに安定したリターンが期待できる。
少額の積立でも大きな資産になる
毎月3万円〜5万円の積立であっても、長期運用による複利効果を得ることで資産は大きく膨らむ。
複利効果とは、運用益が再投資されることで雪だるま式に資産が増える現象であり、運用期間が長ければ長いほどその効果は大きくなる。
非課税効果を長期間受けられる
新NISAでは、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の両方で得られる運用益が非課税となる。これにより、長期間にわたって税金を抑えながら資産を増やせる。
通常、運用益には約20.315%の税金がかかるが、新NISAを活用すればその分の税金が免除されるため、長期的な資産形成にとって大きなメリットとなる。
40代は新NISAの「つみたて投資枠」から始めよう

新NISAにはつみたて投資枠および成長投資枠の2種類の投資枠があるが、40代がまず着手すべきは「つみたて投資枠」だ。
つみたて投資枠は少額からでも使いやすく、金融庁が認めたファンドのみが対象となっているため、元本割れのリスクを抑えながら資産を増やしていくことが期待できる。
40代であれば20年程度の運用期間が確保できるため、豊かな老後に向けて着実な運用が可能だ。
つみたて投資枠の基本概要
| 非課税保有期間 | 無期限 |
|---|---|
| 投資方法 | 積立投資のみ |
| 年間投資枠 | 120万円 |
| 非課税保有期間限度額 | 成長投資枠と合わせて1,800万円まで |
| 対象商品 | 長期の積立・分散に適した一定の投資信託 |
| 対象年齢 | 18歳以上 |
つみたて投資枠では、年間120万円(毎月10万円)までの積立投資が行える。運用益や分配金に税金がかからないため、複利効果を最大限に活かせる点が大きなメリットだ。
購入できるのは金融庁が厳選したファンドやETFに限られているため、投資初心者でも安心して運用商品を選びやすい。
つみたて投資枠の特徴・メリット
新NISAの「つみたて投資枠」は、長期にわたる分散投資や積立投資をベースとする仕組みで、老後の生活資金の確保や趣味・娯楽の充実を目指す40代におすすめの投資方法だ。
投資によって得られる運用益や分配金が非課税となり、複利効果の恩恵を享受しつつ、将来に向けての資産形成を図れるという魅力がある。
加えて、購入できる商品は、金融庁が厳選したファンドやETFに限られているのも特徴的だ。
これらの商品は、長期での運用にも利用しやすいように信託報酬(運用コスト)が低く、分散投資効果が期待できるファンドが中心となっているため、どんな商品を選べば良いかわからないという人にも利用しやすいだろう。
さらに、つみたて投資枠では、毎月一定額を自動的に積み立てるのが基本的な投資方法だ。
これによって、「安いときに多く買い、高いときに少なく買う」というドルコスト平均法の恩恵を受けられる。
購入単価を平準化することで、相場の変動リスクを抑えながら長期的に資産を増やすことができるのだ。
新NISAを始める40代必見!おすすめ銘柄と選び方

40代が新NISAを始める場合は、まずは投資信託での資産運用がおすすめだ。
プロに運用を任せられて、複数の銘柄に分散しながら投資を行えるため、リスクを抑えながら順調に運用を継続しやすい。
特に、新NISAのつみたて投資枠を活用すれば、税負担を抑えながら効率よく資産運用を行えるのも魅力的だ。
ここでは、銘柄選びのポイントや投資家に人気のある銘柄を紹介していく。
新NISAで銘柄を選ぶときのポイント
新NISAでの投資商品を選ぶ際は、まずはつみたて投資枠で購入できるかどうかをチェックしよう。
対象となるファンドを選べば、非課税で効率よく運用できるだけでなく、金融庁のお墨付きとも言えるファンドに投資できるというメリットを得られる。
また、これらのファンドの中では、さらに以下のようなポイントを比較して選ぶのがおすすめだ。
- 運用コスト(信託報酬)の低さ
- 長期運用では信託報酬の差が運用成果に大きな影響を与えるため、なるべく運用コストの低いものを選ぶのがおすすめ
- 投資対象のわかりやすさ
- どの地域(国)のどんな資産にどのような運用方針で投資しているかを確認する
- 運用パフォーマンスは順調か
- 過去の基準価格チャートや純資産総額などから現在も安定したパフォーマンスが出ているかチェックする
40代に人気のある新NISAおすすめ銘柄
具体的に、40代にどのような投資信託が人気なのか確認していこう。
以下は、楽天証券の40代ユーザーがNISA口座で購入している銘柄ランキングだ。
| 順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 1位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 66685.32 | 0.0814% |
| 2位 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 55517.09 | 0.05775% |
| 3位 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 1408.2 | 0.192% |
| 4位 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 4881.71 | 0.077% |
| 5位 | iFree NEXT FANG+インデックス | 5106.59 | 0.7755% |
ランキングの上位には、運用コストが低いことで人気がある「eMAXIS Slim」シリーズがランクインしている。
どちらも信託報酬は0.1%を切っており、ほとんど運用コストを気にせずに投資できる。
S&P500や全世界の株式にまとめて投資できるインデックスファンドの人気が高いと言える。
【シミュレーション】40代が新NISAで毎月5万円積み立てたら?

40代が新NISAで毎月積立を行うと、どのように資産が増えていくのかシミュレーションしていこう。
積立金額別の運用シミュレーション
以下は、毎月3万円、5万円、10万円をそれぞれ積立投資した際の30年後の運用シミュレーションだ。なお、年利は3%として計算する。
| 毎月の積立金額 | 投資元本 | 運用収益 | 30年後の資産額 |
|---|---|---|---|
| 3万円 | 1,080万円 | 668万円 | 1,748万円 |
| 5万円 | 1,800万円 | 1,114万円 | 2,914万円 |
| 10万円 | 3,600万円 | 2,227万円 | 5,827万円 |
毎月の積立金額が3万円だとしても、30年間コツコツ積立投資を継続すると、運用収益としては約670万円が得られ、30年後の資産額は約1,750万円となる。
もちろん、上記の計算結果はあくまでも試算であり実際の相場の状況によっては想定よりもパフォーマンスが良くない場合もあるが、一つの目安として参考にできるだろう。
5万円、10万円と積立金額を増やすと、その分想定される運用収益も大きくなり、将来の運用資産額も増えていく。
最近では、70歳近くまで再雇用制度やパート・アルバイトなどで働く人も珍しくなく、毎月投資を継続するのはそれほど難しいことではないだろう。
まずは少額からでもコツコツ積み立てることが大事
毎月数万円を投資し続けるのは難しいと感じる方がいるかもしれないが、積立投資を始める場合はまずは数百円〜数千円からでも構わない。
少しずつでもコツコツ投資を継続することで、着実に資産形成を図れるはずだ。
ただし、毎月コロコロと積立金額が変わってしまうと、購入単価を平準化するドル・コスト平均法の効果が薄まってしまう。
リスク分散をしながら積立投資を継続するためにも、生活費を圧迫しない範囲でどの程度の金額なら投資に回せそうかもしっかりとシミュレーションしてみよう。
40代は新NISA「成長投資枠」の併用もおすすめ

ここまで、新NISAのつみたて投資枠での投資をメインに紹介してきたが、投資資金に余裕のある40代の場合は「成長投資枠」の併用もおすすめだ。
ここでは、成長投資枠の特徴や活用方法などをチェックしていこう。
成長投資枠の基本概要
| 非課税保有期間 | 無期限 |
|---|---|
| 投資方法 | 積立投資・スポット投資 |
| 年間投資枠 | 240万円 |
| 非課税保有期間限度額 | 1,200万円まで |
| 対象商品 | 上場株式・投資信託等 |
| 対象年齢 | 18歳以上 |
成長投資枠で購入できるのは、年間で240万円までとなっている。
対象商品には個別株やETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)など幅広い資産が含まれ、インデックスファンドだけではなく比較的リスクの高い資産にも投資できるのが特徴だ。
当然ながら運用益は非課税で受け取れるため、大きな利益を狙いたい場合には成長投資枠の活用が有効である。
成長投資枠の特徴・メリット
成長投資枠では、以下のような商品に投資が可能だ。
- 投資信託
- ETF・REIT
- 国内株式
- 外国株式
つみたて投資枠に比べて幅広い商品に投資できるため、投資する資産クラスの分散を図りたい方や、ハイリスク・ハイリターンな投資をしたい方、株式の配当や優待狙いで投資をしたい方にも利用しやすい。
特に、個別株式の場合、企業の成長に応じて株価が大きく上昇する可能性があり、数年で資産が倍増するケースも珍しくない。
ただし、こうした個別株への投資には相応のリスクも伴うため、複数の銘柄の分散保有を心がけることが重要だ。
また、2つの枠を同時に使用することで、年間上限は360万円にまで増えるため、まとまった資産の置き場としてもぴったりだ。
加えて、成長投資枠では高配当株やインカムゲイン(配当収入)戦略も実行可能だ。高配当株に投資することで、株価の上昇だけでなく、定期的な配当収入も得られる。
成長投資枠の非課税メリットを活かせば、配当金に対する課税も免除されるため、長期的に安定した収益を得られるだろう。
このように、成長投資枠ならではの魅力もたくさんあるため、運用ニーズや投資資金の金額に応じて、2つの枠をうまく使い分けるのが大事だ。
成長投資枠の活用方法
成長投資枠の活用方法は、大きく分けると以下の3種類だ。
- つみたて投資枠と同様の商品で積立投資
- つみたて投資枠にないアクティブファンドに投資
- つみたて投資枠では投資できない株式に投資
つみたて投資枠と同様の商品に投資する場合、単純に投資できる金額が大きくなる。投資する商品が増えるわけではないので、銘柄の管理が楽だというメリットがある。
全世界型やバランス型のファンドのみで運用したいという方は、両方の枠で同様の商品に投資するのも良いだろう。
また、つみたて投資枠ではコストを抑えやすいインデックスファンド、成長投資枠ではリターンを狙えるアクティブファンドといったように非課税枠によって投資対象を分けるのも一つの手だ。
インデックスファンドであってもつみたて投資枠では購入できない銘柄も多いため、こうした銘柄も成長投資枠で購入できる。
参考までに、SBI証券のNISAランキングからつみたて投資枠では購入できない銘柄を抜粋して紹介する。
| ファンド名 | 純資産(百万円) | 信託報酬 |
|---|---|---|
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 273,391 | 0.2035% |
| SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 1,948,222 | 0.1238% |
| SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 16,651 | 0.1838% |
「高配当株に投資したい」「金に投資する投資信託に興味がある」といったように、具体的にテーマを絞って投資したい場合、成長投資枠が適しているだろう。
また、同じくSBI証券のNISA口座における国内株式の週間買付金額ランキングは下記の通りだ。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 5016 | JX金属 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 9432 | 日本電信電話 |
| 9104 | 商船三井 |
| 4063 | 信越化学工業 |
配当が高い銘柄やすでに成熟している安定企業などに投資したい場合も、NISAの成長投資枠を活用するのがおすすめだ。
新NISAでは、株式の配当なども非課税で受け取れるため、高配当株等とも非常に相性が良い。
40代が新NISAを始めるときに知っておきたい注意点

40代が新NISAを始める際は、いくつか注意したいポイントがある。
40代は老後資金の準備を本格的に考え始める時期であり、資産運用の選択ミスが将来の生活に大きく影響する可能性があるため、リスク管理や資産計画は慎重に行うことが望ましい。
ここでは、40代が新NISAを活用する際に注意すべきポイントを詳しく解説する。
新NISAは損益通算・繰越控除ができない
新NISAの運用益は非課税となる一方で、損失が発生した場合でも損益通算や繰越控除ができない点に注意が必要だ。
通常の特定口座では、他の投資で得た利益と損失を相殺(損益通算)したり、損失を翌年以降に繰り越して税負担を軽減したりといったように、投資で出たマイナス分を税負担の軽減に役立てられる。
しかし、新NISAでの投資ではそもそも利益も損失も税務上ないものと取り扱われるため、損失が出た場合も他の口座の利益と相殺する仕組みが存在しない点に気をつけよう。
余剰資金の範囲内で投資するのが鉄則
新NISAの活用にあたっては、余剰資金の範囲内で投資することが鉄則だ。
40代は教育資金や住宅ローン、老後資金の準備など、支出が多いライフステージなので、貯蓄や生活費の管理は適切に行う必要がある。
万が一、市場環境が悪化した場合でも生活資金に影響が出ないよう、余剰資金で運用することが大事だ。
新NISAは長期運用が前提の制度であるため、短期間で利益を求めず、無理のない範囲で積み立てを継続することがおすすめだ。
利益を追求しすぎて過度なリスクテイクは危険
成長投資枠では個別株やETF、REITなど、リスクの高い資産への投資が可能だが、利益を求めすぎて過度にリスクを取ってしまうことは避けた方が良い。
40代は資産形成の最終段階に差し掛かる時期であり、大きな損失を被るとリカバリーする時間的余裕が少ない。
特に、成長投資枠で個別株に集中投資する場合、リターンを狙う一方で大きな価格変動リスクにもさらされるため、バランスの取れたポートフォリオの構築が必要だ。
老後に向けた資産形成のコアとなる部分はつみたて投資枠でコツコツとインデックスファンドに投資を行い、ボーナスなどで余剰資金が出た分は成長投資枠で個別株に投資するなど、うまく投資枠を使い分けるのもおすすめだ。
長期目線で運用計画を立てて定期的に見直す
新NISAは長期運用が前提の制度であり、短期的な相場変動に一喜一憂する必要はない。
ただし、ライフステージや市場環境の変化に応じて運用に対する考え方やニーズは変わるケースが多いため、運用計画を定期的に見直すことが重要だ。
例えば、子どもの教育資金の準備が終わった後は老後資金への比重を高めるなど、資産配分の見直しを行うことで、より安定した資産形成が可能となるだろう。
少なくとも年に1回は運用状況を確認し、必要に応じてポートフォリオの調整を行うことが望ましい。
40代は新NISAを始めるべき!悩みは専門家に相談しよう

ここまで、40代が新NISAを活用すべき理由や活用方法のポイントについて解説してきた。
しかし、「投資についての知識がないから新NISAを始めるのが不安」「自分の場合はいくら積立するのが適切かわからない」などと悩んで、なかなか投資に踏み切れない人もいるだろう。
そのような方は、資産運用の専門家に新NISAでの投資方法を相談するのがおすすめだ。
新NISAで運用方法に迷ったら資産運用の専門家を頼るべき
新NISAでどの銘柄に投資するかや、毎月どのくらい運用に回すべきか迷ったら、資産運用の専門家に相談してみよう。
資産運用の専門家には、FP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、銀行や証券会社の担当者などが挙げられる。
ファイナンシャルプランナーは、ライフプランの設定や家計の見直しなどを手助けしてくれつつ、資産運用の基本について教えてくれる。
ただし、金融商品仲介業者としての登録を受けていないFPの場合、具体的な商品・銘柄についての提案やアドバイスはできないため注意しよう。
新NISAについてまずは大まかに理解したい、現在の家計の状況から適切な投資金額を教えてほしい、といった方におすすめだ。
IFAは、特定の金融機関に属さずに、顧客に資産運用についての提案や金融商品の仲介を行う専門家だ。
具体的な個別商品の提案から購入後のサポートまで行ってもらえるため、実際に投資を今から始めたい、すでに投資を行っているという人にも適しているだろう。
報酬形態やサービス内容は業者やアドバイザーによって異なるため、あらかじめよく確認するのをおすすめする。
証券会社や銀行の担当者に相談すると、特にその会社で取り扱っている金融商品についての深い知識をもとにしたアドバイスを受けられる。
ただし、自社で取り扱っている商品以外についての知識が薄かったり、担当者の営業ノルマに提案内容が左右されたりするケースもある点に注意が必要だ。
専門家に相談することで得られるメリット
新NISAでの運用を専門家に相談することで、正しい知識や豊富な経験に基づくアドバイスを受けられるというメリットを得られる。
新NISAのつみたて投資枠では、金融庁が長期の分散投資に適していると認めた投資信託のみが運用対象となっているが、それでも購入できるファンドの数は2025年3月時点で300本以上にも及ぶ。
この中から自分の運用ニーズに最適な商品を選び出すのは、初心者にとってはなかなかハードルが高いだろう。
資産運用の専門家に相談することで、自分の運用ニーズを洗い出し、リスク許容度や求めるリターンに適した投資商品を選びやすくなるはずだ。
資産運用の専門家には上記で紹介した通り様々な種類が存在するので、それぞれの違いを見極めた上で、自分に合った専門家を選択しよう。
「何から始めたら良いかわからない」「資産運用の専門家をどのように探せば良いか知りたい」とお困りの方は、「資産運用ナビ」を活用してみてほしい。
自分の年齢や金融資産、相談内容などを入力するだけで、自分に適したアドバイザーが自動的に検索・表示される。
複数のアドバイザーのプロフィールを比較して、相談するアドバイザーを選択できるため、納得感を持って面談に臨めるだろう。
定年後のライフプランの作成や資金のシミュレーションなどもプロに任せられるため、今までお金についてあまり考えてこなかったという人にもおすすめのサービスだ。
これから新NISAでの運用を始めたいという方は、ぜひ「資産運用ナビ」を利用してみてほしい。
40代の新NISAはつみたて投資枠から始めるのがおすすめ

40代から新NISAを活用すれば、老後資金の準備や将来の資産形成に大きく役立つ。投資初心者の場合は、つみたて投資枠から始めてみるのがおすすめだ。
長期の分散投資に適した投資信託に投資することで、安定した運用成果が期待できるだろう。まずは少額からでも構わないので、コツコツ続けてみよう。
加えて、貯蓄に余裕がある場合は、成長投資枠の活用も検討してはいかがだろうか。
つみたて投資枠で安定した資産形成を行いながら、成長投資枠で高リターンを狙うことで、バランスの取れた運用が可能だ。
新NISAについてわからないことや不安なことがある場合は、資産運用の専門家に相談するのを推奨する。
資産運用の専門家には、FP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、証券会社・銀行の担当者などが挙げられ、それぞれ特徴や相談できる内容、サポートなどが異なる。
自分に適した資産運用の専門家を選び、信頼して運用について相談できるパートナーを見つけることで、長期的に安定的な資産運用を行いやすくなるはずだ。
自分にどんな専門家が適しているかわからない場合は、「資産運用ナビ」を利用してみてはいかがだろうか。
年齢や相談内容、金融資産などを入力するだけで、自分にぴったりのアドバイザーが検索されるサービスだ。
検索されたアドバイザーの得意分野や保有資格などは一覧でチェックできるため、複数のアドバイザーを比較して選ぶことも簡単だ。
新NISAについて専門家に相談してみたいという方は、ぜひ「資産運用ナビ」を利用してみよう。