- 新NISAを最短の5年で使い切るべきか迷っている
- 新NISAを5年で使い切るときのメリット・デメリットが知りたい
- 新NISAの枠1,800万円を使い切った後はどうしたらいいのか知りたい
2024年からスタートした新NISAでは、非課税投資枠が大幅に拡大され、生涯で最大1,800万円まで投資することが可能となった。
この非課税枠は最速で5年で全て使い切れるが、短期間で使い切るべきか、時間をかけて使い切るべきかは、投資目的やリスク許容度によって異なる。
本記事では、新NISAの生涯投資枠を5年で全て使い切る場合と、時間をかけて使っていく場合のメリット・デメリットを比較し、どのように投資ペースを決めていけば良いかを解説していく。
新NISAの枠を使い切った後の運用のポイントや運用に迷った場合にどうすれば良いかなども紹介するため、ぜひ参考にしてみてほしい。
新NISAは最短5年で使い切ることができる

2024年から始まった新NISAでは、「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2種類の投資枠を利用できる。
それぞれ投資対象や投資方法が異なり、自分の運用ニーズに合わせて使い分けやすいというメリットがある。
二つの枠の両方に同時に投資を行っても良いし、どちらの枠のみを活用しても構わないが、運用できる上限は一生涯で1,800万円までと決められている。
なお、このうち成長投資枠の範囲は1,200万円までとなっている点にも注意が必要だ。
また、年間の投資可能額については、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円となっており、二つの枠を最大限に利用すると年間360万円まで投資可能だ。
つまり、つみたて投資枠で毎月10万円(年間120万円)、成長投資枠で毎月12万円(年間240万円)というペースで投資を続ければ360万円×5年間=1,800万円となり、最短5年で非課税限度額を全て使い切れるという計算となる。
新NISAを「5年」で使い切るメリット・デメリットとは

非課税枠は最短5年で使い切れるものの、早く非課税枠を使い切ることが本当に良いことなのだろうか。
まずは、最速である「5年」で使い切るメリット・デメリットを順番に確認していこう。
5年で使い切るメリット
非課税枠を5年間で使い切ると、非課税の恩恵を早期に最大化できるというメリットがある。
短期間で投資元本を最大化できるため、それ以降の運用によって大きく資産を増やせる可能性がある。
以下は、毎月の積立金額及び運用期間別のシミュレーションだ。
どのケースも30年間運用し、運用利回りは年3%と想定する。
| 積立額 | 投資期間 | 投資後の 運用期間 | 元本 | 30年後の運用総額 (元本+運用収益) |
|---|---|---|---|---|
| 毎年360万円 (30万円/月) | 5年 | 25年 | 1,800万円 | 約4,066万円 |
| 毎年180万円 (15万円/月) | 10年 | 20年 | 1,800万円 | 約3,787万円 |
| 毎年120万円 (10万円/月) | 15年 | 15年 | 1,800万円 | 約3,533万円 |
| 毎年60万円 (5万円/月) | 30年 | ー | 1,800万円 | 約2,901万円 |
投資した元本は1,800万円で変わらないが、30年後の運用収益は大きく変わってくる。
早めに枠を使い切ることで、その後の運用期間が長くなり、その分複利効果を生かしやすくなるのだ。
加えて、早期に投資元本を最大化することで、投資先の資産が大きく上昇した時の利益幅も大きくなり、非課税の恩恵も最大化できる。
利回り5%で運用を行った場合、投資元本の違いによる運用収益の違いは下記のとおりだ。
| 投資元本 | 5年 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 638.1万円 | 814.4万円 | 1,326.6万円 |
| 1,000万円 | 1,276.3万円 | 1,628.9万円 | 2,653.3万円 |
| 1,800万円 | 2,297.3万円 | 2,932.0万円 | 4,775.9万円 |
上記の通り、投資元本が大きく運用期間が長い方が、資産を効率的に増やしやすいことがわかる。
5年で使い切るデメリット
一方、枠を5年で使い切ってしまうと、市場が大きく下落した際に損失が大きくなりやすいというデメリットがある。
5年間で一気に投資を行うため、購入時期の分散によるリスクヘッジ効果が働きにくく、相場の変動リスクを直接受けやすくなってしまう。
また、毎月30万円の投資が必要となるため、生活費や貯蓄に余裕がないと、日々の生活に必要なお金の資金繰りが厳しくなってしまう点にも注意が必要だ。
新NISAを「時間をかけて」使い切るメリット・デメリットとは

続いて、時間をかけて枠を埋めていく場合についてチェックしていく。
どんなメリット・デメリットがあるのか確認していこう。
時間をかけて使い切るメリット
時間をかけて枠を埋めていくメリットは、少額からコツコツ投資が可能なことだ。
まとまった金額を一気に投資に回せない場合も、毎月少しずつ投資金額を増やしていくことで、着実に資産形成を行える。
また、時間をかけて少しずつ投資を行うことで、投資タイミングの分散によって価格変動リスクを抑えやすくなるのもメリットだ。
一気に投資をしてしまうと、価格が天井に近づいているところで投資してしまう「高値づかみ」が発生しやすくなるが、投資タイミングを分散することで自然と購入単価もばらけやすくなる。
毎月の投資金額を一定にすることで、「高い時には少なく買い、安い時には多く買う」ドルコスト平均法を実践できるのだ。
まとまった金額を一気に投資するわけではないため、運用開始後に投資先の資産が大きく下落した場合も、その後も継続して投資を行うことで暴落のリスクをカバーしやすくなる。
時間をかけて使い切るデメリット
時間をかけて枠を埋めていく場合、少額ずつ長期間にわたって投資するため、非課税の恩恵を最大限に活かしきれない可能性に注意が必要だ。
特に、投資枠の埋め方が遅いと、運用益が非課税で増える時間が短くなり、利益の最大化のチャンスを逃してしまう。
また、投資額が少額のうちは複利効果が十分に働かないため、資産の成長スピードが遅くなることもデメリットといえるだろう。
さらに、時間をかけて投資を続ける場合、相場が好調な時期に積極的に資金を投じられず、後々枠を埋める頃には相場環境が悪化している可能性もある。
相場の波に乗るタイミングを逃してしまうことで、本来得られたはずのリターンを見送るリスクもある。
【結論】新NISAは何年かけて使い切るべきなのか?

ここまで、新NISAの投資枠の使い切り方についてメリット・デメリットを検証してきたが、結論としてはどのように枠を使い切るのがベストと言えるのだろうか。
新NISAは無理に使い切る必要はない
そもそも、新NISAの非課税枠は無理に使い切らなくても大丈夫だ。
NISA口座で運用できる金額は最大1,800万円と大きめに設定されているが、必ずしもこの枠を無理に使わなくても良い。
新NISAは非課税期間が無期限であり、投資枠も翌年以降に繰り越されるわけではないため、計画的に枠を活用することを意識しよう。
しかし、生活資金を圧迫してまで急いで埋める必要はなく、あくまで自分のペースで投資を続けることが重要だ。
効率よく利益を追求するなら最短5年で使い切るのがおすすめ
相場の変動に対してリスク許容度が高く、積極的に資産形成を進めたい人には、最短5年で枠を埋めてしまうのがおすすめだ。
年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)をフル活用すれば、5年で1,800万円の枠を全て埋めることができ、運用益の非課税メリットを最短で最大化できる。
また、まとまった資金を早期に投資することで、複利効果がより大きく働き、資産の増加スピードが加速する可能性も高い。
相場環境が好調な時期に投資すれば、大きなリターンを得られるチャンスも増える。
ただし、短期間で枠を埋める場合、相場のタイミングによっては元本割れのリスクも伴うため、投資先の分散やポートフォリオのバランスには十分な注意が必要だ。
リスクを抑えるなら時間をかけて使い切るのがおすすめ
相場の変動リスクを抑えながら、安心して資産形成を進めたい場合は、時間をかけて枠を埋めていくのがおすすめだ。
少額ずつ長期にわたって投資を続けることで、購入時期を分散できるドルコスト平均法のメリットが活かされ、相場の上下に左右されにくくなる。
さらに、時間をかけて投資することで、生活資金や将来の予備資金にも余裕を持たせることができる。
大きな資金を一度に投資するよりも、余裕資金の範囲で投資を続ける方が、長期的に安定した資産形成が可能だ。
ただし、時間をかけすぎると非課税の恩恵を受けられる期間が短くなり、運用益の最大化を逃すリスクもある。
新NISAに投資するペースは、自分のリスク許容度や資産状況を踏まえて、バランスよく決めることが重要だ。
新NISAの非課税限度額1,800万円を使い切ったら?

非課税枠を使い切った後も、資産を効果的に増やしていくために実践したいことがいくつかある。
ここでは、枠を埋めた後に考えるべきポイントについて詳しく解説する。
定期的に保有商品の見直しを行う
新たに運用できる非課税枠を全て使い切った後も資産運用は続くため、定期的な保有商品の見直しは不可欠だ。
相場環境は常に変化しており、当初選んだ商品が長期的に最適とは限らない。
ポートフォリオ全体のバランスを定期的に確認し、必要に応じて調整することで、リスクとリターンのバランスを維持できる。
また、ライフプランの変化に合わせて運用方針を見直すことも重要だ。
将来の資金ニーズに応じてリスク許容度も変わるため、資産の配分や投資方針を柔軟に調整することで、安心して資産を育て続けることができるだろう。
売却すると翌年度に枠が復活する
新NISAでは、投資枠を埋めた後でも、すでに購入した金融商品を売却すれば翌年度に売却分の枠が復活する仕組みが設けられている。
例えば、1,800万円の枠を使い切った後に300万円分の株式を売却すれば、翌年には300万円分の投資枠が再度利用できる。
この仕組みを活用することで、運用方針を変更したい時や、利益確定を行いたい時にも柔軟に資産の入れ替えができるというメリットがある。
ただし、売却した分の枠はすぐに復活するのではなく翌年度の復活になることや、再利用する場合でも年間の上限(360万円)を超えて投資することができない点には注意しよう。
夫婦で活用すると3,600万円まで投資可能
新NISAは個人単位で非課税枠が設定されているが、夫婦でそれぞれ1,800万円の枠を活用すれば、世帯全体で最大3,600万円まで非課税で運用することが可能となる。
例えば、夫婦で協力してポートフォリオを組み、異なる商品や投資戦略を採用すれば、リスクの分散効果も高まる。
さらに、夫婦それぞれのリスク許容度や資産形成の目的に合わせた投資方針を選ぶことで、家庭全体の資産運用の柔軟性が向上する。
例えば、一方が安定志向でつみたて投資枠を中心に活用し、もう一方が成長投資枠で積極的にリターンを狙うという戦略も考えられる。
夫婦で新NISAをフル活用することで、より大きな資産形成の可能性が広がるだろう。
新NISAを何年で使い切るか悩んだら専門家に相談しよう

新NISAをどのように使い切るかは、個人の運用ニーズや投資可能額、ライフスタイルなどによって異なる。
どのように投資を行うべきか悩んだら、資産運用の専門家への相談がおすすめだ。
新NISAで毎月いくら投資するか悩んだら専門家への相談がおすすめ
新NISAについて相談できる専門家には、FP(ファイナンシャルプランナー)、銀行や証券会社、IFA(独立系ファイナンシャルプランナー)などが挙げられる。
投資に関する知識や経験が少なくても、専門家にアドバイスを求めることで、最適なポートフォリオを組んだり適切な投資金額を決めたりしやすくなる。
ただし、それぞれの専門家によって相談できる範囲や報酬体系、相談後のサポート体制が異なるため、しっかりと比較して検討するのをおすすめする。
新NISAでの運用を専門家に相談すると得られるメリット
新NISAでの運用を専門家に相談することで、自分に合った投資ペースや投資商品についてのアドバイスを受けられるというメリットがある。
また、運用を開始した後もリスク許容度に応じたポートフォリオの見直しや、相場の変動にどのように対応すべきかといった相談にも対応してもらえるだろう。
自分に合った専門家をどのように選べば良いかわからないという方は、「資産運用ナビ」の活用がおすすめだ。
年齢や金融資産などを入力するだけで、自分に適した資産運用アドバイザーが自動的に検索・表示される。
アドバイザーの経歴や保有資格、得意分野などもプロフィールページから確認できるため、自分にとって魅力的な資産運用のパートナーを見つけやすい。
相談したいと思うアドバイザーが見つかったら、そのまま無料相談に進むことも可能なので、ぜひこの機会に利用してみてはいかがだろうか。
新NISAを5年で使い切るべきかは運用ニーズによって異なる

新NISAで利用できる投資枠は、最短5年で使い切ることも、時間をかけてゆっくり埋めることも可能だ。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分のリスク許容度や資産形成の目的に応じた運用方法を選ぶことをおすすめする。
無理に枠を埋める必要はなく、自分のライフプランに合わせたペースで活用することで、長期的な資産形成を安心して進められるだろう。
どのようなペースで投資を続ければ良いか、自分にどんな投資商品が適しているかなど、投資に迷った際は専門家に相談するのも一つの選択肢だ。
「資産運用ナビ」を利用すれば、年齢や金融資産、住まいなどを入力するだけで自分に適したアドバイザーが簡単に見つけられるため、ぜひこの機会に活用してみてほしい。
新NISAは5年で使い切るべきかに関するQ&A








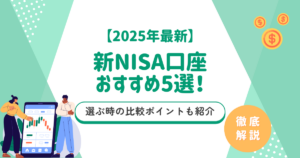

コメント
コメント一覧 (1件)
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。